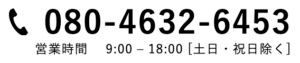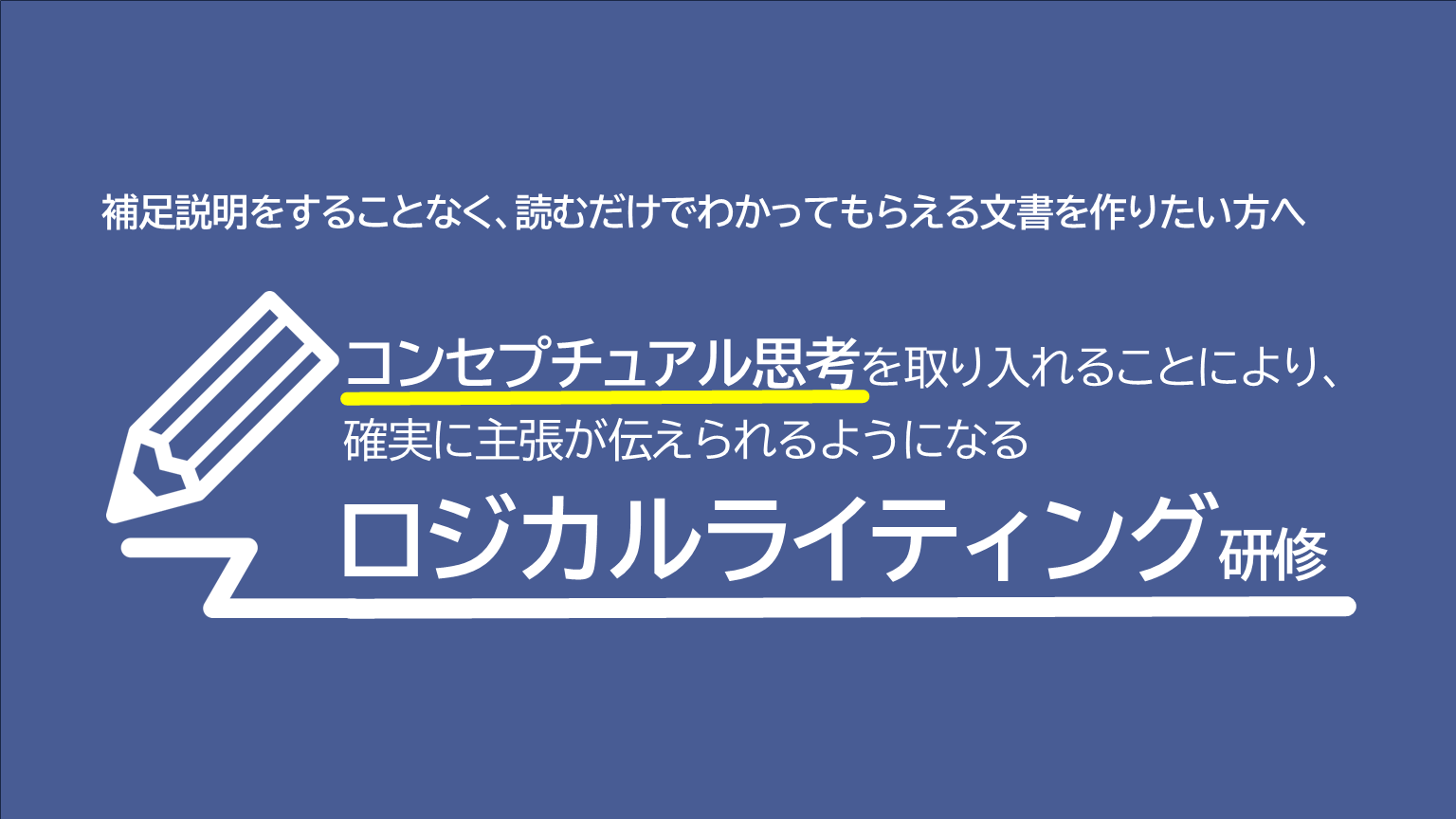
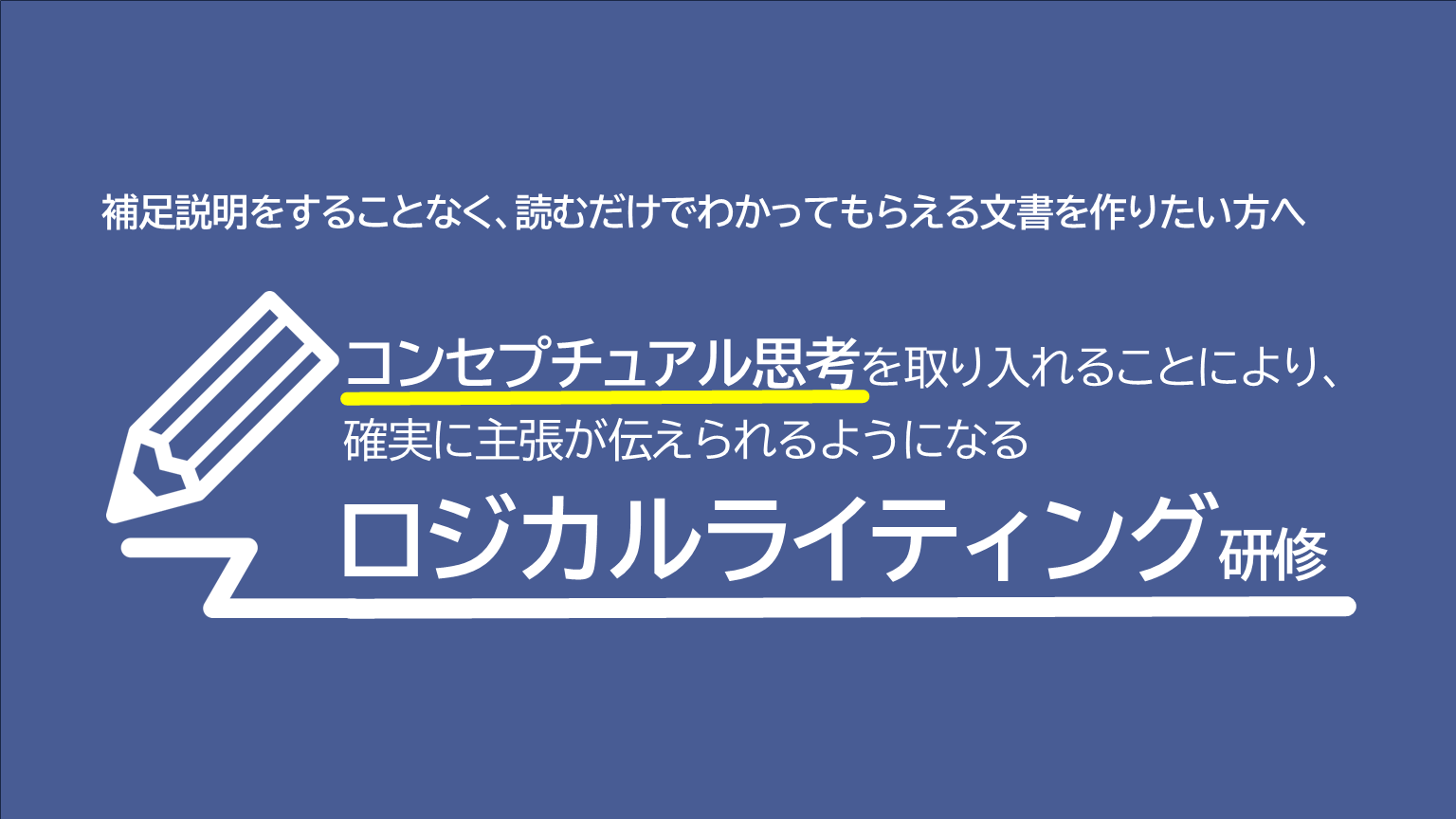
自己成長支援ラボの提供する研修は、理論だけでなく、実践で使える研修です。
多くのロジカルライティング研修では、物事を「分析的」に捉え、「ロジカル」に表現する手法をお伝えしています。
しかし、それだけでは実践で求められえる文書、すなわち「主張が伝わる文書」にはなりません。
実は、主張が伝わる文書にするには、「コンセプチュアル(概念化)思考」も必要なのです。
また、ビジネスで、相手が必要とする文書を作成するには、「誰が読み、読んだ相手に何をしてもらいたいのか」という、読み手を意識し、読み手に期待するアクションを想定するという視点を持ったり、「相手はどういった文書を作成してもらうことを望んでいるのか」と、相手が期待する要素を踏まえるという視点を持ったり、と言った、同じ内容でも、読み手やその時の状況に合わせて、表現や構成を作り直す必要があります。
更に、何でもかんでも1つの表に盛り込んでしまい、解析しながらでないと読み解けなくしてしまったり、「実験・解析結果はこうでした」ということを結論としていて、「結果から、何が言えるのか」を伝えていないなど、理系の方特有のクセにも気づいていただけます。
自分の文章作成スキルを高めたい方、社員の文章の伝達力にお困りの企業様はぜひともご相談ください。
このタイトルを目にすると、文書作成にEQ(マインド)が影響するのか、と疑問を持たれる方も多いと思います。
おっしゃる通りです。
一方、受講をした方からは、「文書作成力をアップさせるためには、スキルやテクニックも大切ですが、文書作成に対するマインドを変える(変なこだわりを捨てる)ことが重要だと思いました!」と言われることが多いです。
これはどういうことかと言いますと、ヒトは、自分の勝手な思い込みによって、知らないうちに、行動に制限を掛けていることがあるのですが、これが、ライティングにおいても同じ、ということです。
また、ヒトは、自分が本当に伝えたいことがわからないまま文章を完成させてしまい、それを口頭で説明しながら始めて、自分が伝えたいたことに気づいたり、相手から、あなたが言っていることは、こういうことですよね?と言われて、改めて自分が伝えていたことに気づく、というようなことがあります。これも、文書作成のために集めた資料を全部盛り込んでそれを整理する、という「(集めた・関係する)情報は、全て盛り込まなくてはならない」という、こだわり(思い込み)の結果で、「何を伝えなければならないのか」「何を伝えたいのか」ということを見失ってしまっていることに起因します。
自己成長支援ラボが提供する、EQ(マインド)を考慮したオリジナルプログラムでは、ライティングのテクニックをお伝えすることに加え、自分の勝手なこだわり・思い込みに気づいてもらったり、自分が本当に伝えたいことに意識をフォーカスしてもらえるようになることで、自分の伝えたいことを、確実に相手に伝えられるようになっていただけます。
多くのロジカルライティングでは、演習で文書の作成をするものの、実際に自身が作成した文書を添削してもらえることはまれ、です。
一方、自己成長支援ラボが提供する研修では、受講生の方から、自身が作成した文書を提出いただき、それを添削し、その内容を講義の中で共有します。
受講された方からは、
・・・など、皆さんの前で添削結果を公開されることは恥ずかしいものの、自身のクセやこわだりなどに気づいていただけることに加え、様々な事例を確認することで、多くの気づきを持ち帰っていただいています。
自己成長支援ラボにご依頼いただけた場合、弊社で準備しているオリジナルプログラムを提供するだけでなく、御社に以下のような内容をご提案いたします。
これまでのロジカルライティングは、ツリー構造で、主に分析的に文章を書くことに主眼が置かれていました。
そして、より結論を体系的に導けるよう、ピラミッドストラクチャーと言った、構造的に文章を書くことも教えられてきました。
しかし、これだけでは、主張のある/主張を伝える文章を作ることはできません。
なぜなら、主張を明確にする過程で、文章を要約し、タイトルをつける際には、文章内に書かれている用語をそのまま持ってくる(抜粋してくる)のではなく、文章を俯瞰し、文章に書かれている内容を概念化(抽象化)することが求められるためです。
言い換えると、「要は」と一言で表す際に、書かれている文章を短くして(要約して)表現するのではなく、書かれている文章の中心となる考えやテーマである要旨(論拠)を明確にすることが求められるためです。
そこで、弊社が提供する「主張が伝わるロジカルライティング研修」では、ロジカル思考力+コンセプチュアル思考力のそれぞれの強化を図り、最終的には「要旨」「論拠」が伝わるような文章を作ることができるようになってもらいます。
2日間(1日は、10:00-17:00)のプログラムを標準としています。
第1日目と第2日目の間には、1週間以上の間隔を置き、第1日目で受け取った文書をその間で添削し、2日目に添削結果を説明するようにしています。
なお、第1日目の開催1週間以上前に、受講者から文書を受け取ることができれば、第1日目、第2日目を連続して行うことができます。
添削についてですが、過去の経験から、添削を入れると入れないとでは、受講者の気づきや持ち帰りに、ひいては満足度が大きく変わるため、事務局として手間はかかるものの、添削を入れることをお勧めします。
第1日目:理論編:自分の主張を構造で提案・報告する
| NO. | タイトル | 概要 | 区分 |
| 1 | あいさつ | オリエンテーション/講師紹介 | 説明 |
| 2 | イントロダクション | 目的とゴールイメージを明確にする | 演習 |
| 3 | メッセージを意識する | 読み手は、文書から字面ではなく、メッセージを読み取っていることを知る。また、人は、納得しないとアクションを起こしてくれないことを知る。そして、これからはメッセージを通して納得性が得られる文書作りが必要であることを学ぶ。 | 講義 |
| 4 | 相手が納得する論理性の根拠 | 論理的な文書を構成する要素が、三角ロジックで表されることを知り、その中の論拠が、実はメッセージであり、納得性を高める要素であることを知る。なお、論拠は文章の表には出て来ないことを知る。 | 講義 |
| 5 | 納得性を高める方法 | 多くの文章が、演繹法と帰納法の組み合わせであることを知り、根拠と主張の背景には演繹法が、論拠の整理には、帰納法が、それぞれ使われていることを理解する。 | 講義 |
| 6 | 因果関係を意識する | 人は、文書の整合を確認する(論理性を確認する)際に、因果関係に着目することを知り、演繹法の確からしさを確認する手段が因果関係であることを理解する。 | 講義 |
| 7 | 構造化により事実の中から事実に基づく主張(論拠)を見出す | 人は、構造化を図る(ピラミッドストラクチャーを形成する)ことで、事実に基づく主張(論拠)が見えてくることを知り、帰納法から主張を導き出す方法を理解する。なお、その際には、MECEであることや、ディメンジョンを揃えること、タイトル付けが重要であることも知る。 | 講義 |
| 8 | 構造から主張を導き出す(演習) | クレームの集約を通じて、構造的な報告書を作成し、構造から主張を導くことを実践する。 | 演習 |
| 9 | 合理的に要約する | 論理的な文章を作成する中で、事実を整理し、タイトル付けをする際には「単なる要約」ではなく「概念化」が、また、全体の主張や論理構成を考える際には、「俯瞰力」「類推力」が、それぞれ必要であることを知る。このことから、論理的な文章を作成するためには、分析的な思考だけでなく、統合的な思考が必要であることを学ぶ。 | 講義 |
| 10 | まとめ |
第2日目:実践編:相手が望む資料に作り替える
| NO. | タイトル/テーマ | 概要 | 区分 |
| 1 | あいさつ | オリエンテーション/本日のアジェンダ紹介 | 説明 |
| 2 | 文書の相互確認 | 文書を受講者間で相互に確認する他、講師から受講者のレポートの添削結果を報告する。
分析:構造、主張を明らかにする。 提案:改善点、或いは主張を明確にするための新しい構造の提案をする。 |
講義 |
| 3 | 問題を解決する力をつける | 問題(課題)は自分で認識するものであることを知り、同じ事実であっても、問題提起・分析・報告は、扱った人の捉え方に基づく主張が反映され、それぞれ異なることを学ぶ。 | 講義 |
| 4 | 問題を解決する力をつける(演習) | フレームワークを用いてアンケートを集約し、報告書を作成する。同じアンケート結果であっても、捉え方に基づく主張によって異なる構成・報告になることを知る。(グループ演習) | 演習 |
| 5 | 相手のアクションを促す文書を作成する | 同じ事実であっても、立場によって、課題認識・受け止め方(イシュー)が異なることを知り、相手の期待に沿う・受け止められやすい文書を作成することが、最終的に、相手にとってわかりやすく、「通る」資料になることを知る。 | 講義 |
| 6 | 相手のアクションを促す文書を作成する(演習) | エレベータートークができるよう、自分の主張のある文書を要約すること、並びにエレベータートークを通じて、「概念化を取り入れた要約」「打診」の技術を体得する。(グループ演習) | 演習 |
| 7 | 相手のアクションを促す文書を作成する(演習) | クライアントの意図、自分の実現したい意図、上司の期待をそれぞれ理解しつつ、ビジネスの現場では最終的には相手が認識している課題を解決する文書の作成が求められていることを知る。
なお、演習では、上司の意向を反映した、上司向けの報告書を作成することを通じて、同じ事実であっても、相手が求める表現に変えることで、受け入れられやすい報告になることを知る。(グループ演習) |
演習 |
| 8 | 目的に応じて事実を上手く使う力をつける | 単独の事実だけでは主張を伝えにくいが、意図をもって説明をしたり、比較をすることによって(比較対象を工夫することによって)主張を導き出せることを知る。 | 講義 |
| 9 | 目的に応じて表現を変える力をつける | グラフの作成方法、報告者への説明方法など、相手が受け止めやすくなるテクニックを紹介し、総合的にコミュニケ―ション能力を高める方法を知る。 | 講義 |
| 10 | まとめ | この研修で得た知識をどのように反映したいか、報告してもらう | 講義 |
STEP1 お問い合わせ・ご相談
STEP2 ご要望・ニーズのヒアリング
受講者が書かれている文書などを入手し、受講者のクセや、開発すべきスキルに合わせたプログラムを設計します。
STEP3 研修プランのご提案
STEP4 研修の実施、場合によっては課題の設定
STEP5 研修のフォローアップ
課題の添削等を行い、スキルの定着化を図ります。
STEP6 アンケート集約
昭和41年、鳥取県生まれ。現在は東京在住です。
コンサルティングファームでの経験を通じてロジカルライティングスキルを身に付けました。
その後、事業会社に転職し、企画部門における企画書作成や、経営における重要事項の意思決定を求めるような提案書・企画書作成業務を何なくできるようになったものの、与えられたテーマの企画はすぐに通るのに、自ら1から企画した企画書はなかなか通らないといった苦しみに直面しました。
その時に学んだことは、主張を伝えるには、ロジカルライティングスキルだけでなく、主張を構成する力(ロジカルライティングスキル+コンセプチュアルスキル)が必要であることに気づき、それを文書作成時に取り入れることで、圧倒的に通りやすい企画書・提案書を作成できるようになりました。
その結果、会社における自分の存在価値が高まることを実感し、これまでとは全く異なる影響力を身に付けることができました。
そこで、相手に伝わる文章を作成する能力を高め、ビジネスにおけるパフォーマンスを高めることで、影響力をつけていくような成長をしたいという方に、そのスキルを伝達していきたいという思いから、「主張が伝わるライティング研修」を行うようになりました。
自己成長支援ラボは、ご自身の影響力を付けたい、或いは影響力のある後継者を育てたい、といった、個人や組織の継続的な成長をお手伝いする教育機関です。社員の研修のことでお悩みでしたらご相談ください。
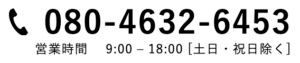
一般的なロジカルライティング研修もできますし、特定の文書作成に焦点を当てたプログラムにカスタマイズすることも可能です。
KISTEC(地方独立行政法人 神奈川県産業技術総合研究所)で年1回、複数年開催しており、同一企業様から、リピートの受講をされています。
研修内容次第で異なりますので、詳細はお問い合わせください。
特に、管理職の場合は、一般職に指導する立場になる一方、自らが企画者・提案者として会議資料等を作る場合もありますので、管理職の方も研修対象になります。