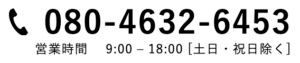肯定型マネジメントとは、主に部下の行動や発言を否定せずに、肯定的に受け止めるマネジメント手法です。部下の自己肯定感を高め、モチベーション向上や仕事へのエンゲージメントを高める効果が期待できます。
肯定型マネジメントは、これまでの「危機感を煽り、緊張感を強いるマネジメント」とは大きく異なり、新しいことに勇気を持って挑戦し、失敗しても許容し合える中、成功するまで応援し続けるなど、互いに良い所・強みを伸ばせるよう、協力し、支援し合い、個人・チーム・グループ・組織のパフォーマンスを最大する組織風土を醸成しながら常に成長していくという「信頼、安心・安全に基づくマネジメント」です。
あなたの悩みは、「~ない」という全て否定で表現されています(笑)。
これらは、あなたが「肯定型マネジメント」をすることで、全て「~してくれる」に変わり、解消されます。
部下の提案や意見を批判したり否定したりするのではなく、まずは肯定的に受け止めることから始めます。
部下の努力や成果を積極的に褒め、肯定的なフィードバックを伝えます。
部下の成長を応援し、必要なアドバイスやサポートを提供します。
部下の気持ちや状況を理解し、共感してあげるように努めます。
部下が自分自身の価値を認め、自信を持って仕事に取り組めるようにサポートします。
特に、以下の3つは、肯定型マネジメントを導入する前に、あなた(キーパーソン)に注意していただく事項として挙げさせていただきます。
ですので、部下に変わってもらうように指導するのではなく、最初にあなたが変わる必要があります。
ですので、あなたの視点を部下に押し付けるのではなく、場合によっては、部下の視点をあなたが受け止めた上で、あなたの視点を捉え直してもらう、ということで、これも、最初にあなたが変わる必要があります。
ここでは、組織構成員の自己肯定感を上げる、としていますが、その中には、あなたも含まれます。そういった意味では、あなたの自己肯定案を上げていただくことが先、となります。
ということから、以下の考えをお持ちの場合は、全肯定マネジメントを導入されない方が、幸せかも知れません。
なお、改めてお知らせしますが、肯定型マネジメントは、あなたに変わっていただく必要はありますが、だからと言って、相手を「腫れ物に触る」ような扱いをしたり、これまで以上に相手に「忖度する力」をつけることではありません。
あなたには、関係者を尊重しつつも、アサーティブに、堂々と自分の考えを持ち、実行していただくだけで、これまでとは異なる影響力がついてきますので、ご安心ください。
肯定型マネジメントは、主に、部下の自己肯定感を高め、モチベーション向上、仕事へのエンゲージメントを高める効果が期待できるマネジメント手法です。一方で、あなた自身の自己肯定感も高まり、これまでと異なる方法で、周囲への影響力を行使していただけるようになります。
自己成長支援ラボが実施する肯定型マネジメントプログラムは、ちまたで行われているリーダーシップ研修やマネジメント研修とは異なります。
その違いとは、その導入プログラムに「EQ」「認知科学」「脳科学」の要素をふんだんに取り入れていることが特徴として挙げられます。
そこで、ここでは、「EQ」「認知科学」「脳科学」の要素が入ることで、どのようなプログラムになっているのか、簡単に説明します。
これまでのリーダーシップ研修やマネジメント研修が、IQを刺激するものが多かったですが、この肯定型マネジメント研修は、EQを意識して使っていきます。
ビジネスの現場で、EQを使う必要があるの?と真っ先に、疑問を持たれたり、抵抗感を覚える方もいらっしゃると思います。
かという私も、「ビジネスでEQを使うなんて、面倒くさい。全て、論理的に、頭で理解することが大切」という人間でした。
ですので、なかなか受け入れにくいとは思いますが、ここからは、少し、EQについて語らせてください。
例えば、部門の方針説明とかの時に、A、Bのどちらが、部下に受け入れてもらいやすいと思いますか。
A:上から、前年比10%増の売上を達成するように、との指示が出たので、皆でがんばろう!
B:上から、前年比10%増の売上を達成するように指示がきたんだけど、これまでと同じことをやるだけでは、個人的にはちょっと大変かな、と思っているんだ。だからこそ、皆の知恵を貸してくれない?
もちろんAでも(仕事の指示だから)受け入れてくれるとは思いますが、Bの方が、組織とか上司に、協力してあげてもよいかな、って思ってもらいやすいですよね。
その違いは何でしょうか。
Aは、ポジティブに表現していますが、Bは、ややネガティブな表現が入っています。
ここからは、EQ的な説明が入りますが、感情にはポジティブなものと、ネガティブなものがあります。
一般的には、ポジティブな感情を出すように努め、ネガティブな感情は出さない、抑える、という使い方が推奨されていますが、EQを使いこなす能力を高めることで、ネガティブな感情を上手く使いこなせるようになります。
実は、本音を語りながら、ネガティブ感情を上手く表現できるようになると、「人を共感」させる力が発揮でき、相手の「人を支えてあげよう/守ってあげようとする」力を導き出すことができるようになります。
先ほどの例で行くと、「個人的にはちょっと大変かな、と思っているんだ」と、本音の部分にネガティブ感情を入れていることが、EQを上手く使っている部分です。
このように、ネガティブ感情を上手く使いこなせるようになることで、具体的には、例えば、今までは「怒り」でしか伝えることができなかったことが、「怒り以外の方法」で伝えられるようになり、あなたの影響力を圧倒的に高めることができるようになります。
人には、尊厳欲求があります。
尊厳欲求とは、一般的には、「他者から認められ、尊敬されたいという欲求」ということで、マズローの欲求5段階説でも、第4次の欲求になっているため、高次な欲求のように捉えられがちですが、実は、「(自分だけは)尊重されたい、大切にされたい」と思っている、非常にプリミティブな欲求です。
そして、人はそれが脅かされたり、満たされたりしないと、それだけで反抗的な言動を採りがちです。例えば、あおり運転などが社会問題化していますが、そのきっかけは、割り込まれた時に、ハザードランプでお礼を示さなかったり、合流の時に、譲ってもらえなかったりしたことなど、自分を大切に扱ってもらえなかった、尊厳欲求が満たされなかったと感じた時に、出てきてしまいます。
これは、コミュニケーションにも関係しています。
人は、自分の意見を言いたいものですし、その意見を聞いてもらえない、否定されたと感じただけで不満に思ったり、反抗的な言動をとってしまったりします。ですので、表面的な傾聴などをしてしまうと、最初はこっちの話を聞いてくれたと思ったのに、結局は、こっちの話と関係なしに、自分を考えを押し付けられた!、などど、かえって不満を助長させ、人間関係が悪くなってしまいます。
また、人には承認欲求があります。
これも、マズローの欲求5段階説では尊厳欲求と同様、第4次の欲求で、高次の欲求のように捉えられがちですが、これも、実は、「自分の存在を認めて欲しい」と思う気持ちで、プリミティブな欲求です。
そして、これも人は、満たされないと、それだけで反抗的な言動を採りがちです。例えば、朝、あいさつをしたのに、返事が返ってこなかっただけで、その日は不機嫌になってしまったり、自分にあいさつを返してこなかった人は自分を認めなかったと認識し、その日だけでなく、その後についても、好意的な態度をとりにくくなってしまいます。
そこで、認知科学を意識した言動を行ってもらうことで、コミュニケーションや人間関係の構築の仕方を大きく変えてもらえるようになります。これにより、具体的には、互いに認め合いながら変革を進めていくことができるようになり、ギスギスすることなく、温かい気持ちになって、チームワークを発揮したり、チームとしての結束を高めたりすることができるようになります。
「ピンクの像を思い浮かべないでください」と言われたら、どうなりますか。そうです、頭の中は、ピンクの像でいっぱいになります(笑)。
このように、脳は、(~しない、といった)「否定」を受け入れられないのです。
ですから、人に何かを頼むときは、「~しないようにする」ではなく、「~するようにする」と表現できるようになるだけで、相手にとっては受け止めやすく、行動に移してもらいやすくなります。
更に、物事を肯定的に受け止め、肯定的に反応する(一般的には、素直な言動をする)ことで、建設的な意見を出したり、建設的な方向に物事を進めたりすることができるようになります。
仮に、今まで、強く言って反骨心を煽り、モチベーションを引き出そうとしていたとすれば、これからは、きちんとビジョンを語ったり、期待を伝えることで、モチベーションを上げる方法を実践していただきます。
また、脳は少しでも楽をしようとしますし、大きな変化を嫌います。
ですから、難しく、かつ大きな変化を起こすと、リバウンドなど、副作用が発生してしまいます。
従って、脳科学を使いこなすことで、「~するようにする:という肯定的な表現を使い、かつ、少しずつ納得をしてもらいながら物事を進めていくことで、逆戻りをしたり、リバウンドしたりすることなく、着実な変化を行っていけるようにします。
日本人の多くは、ネガティブな感情を「怒り」で表現してきました。
「怒り」で表現されると、ハラスメントを発生させやすいばかりか、受け手は、反抗をしたり、委縮したり、と、素直な(肯定的な)言動ができなくなる環境を作ってしまいます。更に、「怒り」で表現されることが続くと、怒らせないようにしよう、問題を顕在化させないようにしよう、と言った変な忖度が始まり、悪いことは報告しない、といったコンプライアンス的にも問題が発生しやすい環境を作ってしまいがちです。
弊社の推奨するEQ(認知科学)に基づいたコミュニケーション方法では、ネガティブな感情を「怒り」以外の方法で表出させることができるようになるため、ハラスメントやコンプライアンス違反とは無縁の、穏やかで素直な、心温まるコミュニケーションが採れるようになります。
日本人の多くは、自分を卑下したり、謙遜をすることをベースにしたコミュニケーションとなるため、相手を素直に尊重したり、褒めたりすることが苦手です。また、相手を傷つけないように、と配慮したり、相手を不快にさせないように、と過剰に忖度することで、本音が言いづらい関係性を築きがちです。
弊社の推奨するEQ(認知科学)に基づいたマインドをベースにしたコミュニケーションをとることで、早い段階から本音をベースにしたコミュニケーションがとれるようになるため、些細なことでも相談できる関係性が作れ、予防的なマネジメントができる土壌を作ることができます。
これまでのすぐれた経営者・管理者は、物事を「否定的に捉える」、言い換えれば、リスクマネジメントに長けていました。
「失敗しないこと」が、結果的に成功につながる、という考え方もありますが、成功を導く方法は、それだけではありません。
弊社の推奨するEQ(認知科学)に基づいた、物事を「否定的に捉える」のではなく、「そのまま(肯定的に)捉える」ようになることで、石橋をたたいて渡るマネジメントから、自分とは異なる意見を尊重し、受け入れ、新しいことに挑戦する風土を生み出すことができるようになり、緊張感・危機感をベースにしたマネジメントから、安心・信頼に基づくマネジメントに進化させることができます。
これまでのマネジメントは、不確実・不安定な状態に対して、危機感を持たせ、反骨心を煽り、常に変化を求めるスタイルでした。
その結果、このマネジメントスタイルでは、社員は疲弊するばかりか、経営者も社員を信頼することができず、緊張感のあるギスギスした組織風土を生み出してしまっていました。
一方、肯定型マネジメントでは、安心・安全、信頼に基づくマネジメントであり、新しいことに勇気を持って挑戦し、失敗しても許容し合える中、成功するまで応援し続けるなど、互いに良い所・強みを伸ばせるよう、協力し、支援し合い、個人・チーム・グループ・組織のパフォーマンスを最大する組織風土を生み出します。
一方、シン・マネジメントでは、安心・安全、信頼に基づくマネジメントであり、新しいことに勇気を持って挑戦し、失敗しても許容し合える中、成功するまで応援し続けるなど、互いに良い所・強みを伸ばせるよう、協力し、支援し合い、個人・チーム・グループ・組織のパフォーマンスを最大する組織風土を生み出します。
|
これまでのマネジメント |
肯定型マネジメント |
|
| パラダイム | こちらの決めつけ/既知 | 相手の事情/未知 |
| マインド
|
従属 | 自立 |
| 否定的 | 肯定的 | |
| リスク | チャンス | |
| 危機を煽る | 安全・安心を確保する | |
| 建前中心 | 本音中心(アシミレーション) | |
| 見栄・自己肯定感が低い | 自己開示・自己肯定感が高い | |
| マネジメント
|
原因追求 | 解決策 |
| 反省 | 建設的・リカバリー | |
| 決めた方法を遵守 | 目的に沿うのであれば、
方法にこだわらない |
|
| 自分で何とかする | 他人に助けを求める | |
| リスク | チャンス | |
| 見かけのWin-Win
(ギブアンドテイク) |
本当のWin-Win | |
| 人材マネジメント
|
しかる | ほめる |
| 減点主義 | 加点主義 | |
| 欠点を埋める | 利点を伸ばす | |
| コミュニケーション
|
こちらの決めつけた想いを話す | 相手の話を聴く |
| 反応的 | 主体的 | |
| 会議ファシリテーション | 議題中心 | 満足度中心 |
肯定型マネジメントの導入手法は、EQ(認知科学)に基づいた、段階的に行動変容を促す実践的な手法であるため、取り組まれた企業様はほぼ成果を出しています。そして、当初は意図していなかった、新しいマネジメントスタイルを構築することができます。
物事の捉え方が、現状を肯定する形に変わるため、自らの強みを素直に伸ばしていくマネジメントになります。その結果、他に左右されることなく(他の差別化要因にこだわることなく)、オンリーワンのマネジメントになります。
現場の担当者が主体的に行動していくことにより、コミュニケーション方法が、指示・命令から報告・承認型に変わります。その結果、マネジメントスタイルがTOPダウンからボトムアップに変わります。
日々発生する小さな不安を開示・相談してもらえるようになることにより、問題を生じさせる前に対処できるようになります。その結果、問題解決型のマネジメントから、問題の発生を未然に防ぐ、予防的なマネジメントに変わります。
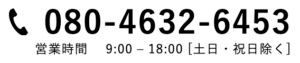
自己成長支援ラボにご依頼いただけた場合、御社に以下のような内容をご提案いたします。
・過去の組織風土調査などの確認や、場合によっては再分析を行います
・研修のご担当者だけでなく、必要に応じて社員の方へのヒアリングを行います
A
ご要望に応じて可能です。
一般的な肯定型マネジメントスタイル研修もできますし、御社の問題解決に焦点を当てたプログラムにカスタマイズすることも可能です。
A
人数は関係ありません。
どの程度の費用がかかるのかは研修の内容次第によって異なります。
まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。
料金の参考はこちら
A
場合によっては2ヶ月ほどかかることもあります。
研修内容次第で異なりますので、詳細はお問い合わせください。
A
経営者、管理、職、一般職とそれぞれ内容が異なります。
まずは経営者、次に管理職となります。
一般職については、経営者・管理者への教育を行った後、必要に応じて、です。
逆に一般職のみでは、効果はありません。
A
研修を受けることで、自ら行動変容を起こせる方もいらっしゃいます。なお、組織に導入する場合は、組織内のコミュニケーション方法(報告・連絡・相談方法や、会議など)を変えたり、キーマンに対してコーチングなどのコミュニケーショントレーニングを行ったり、と様々な方法を提案して実践していくことで変革を起こしていきます。